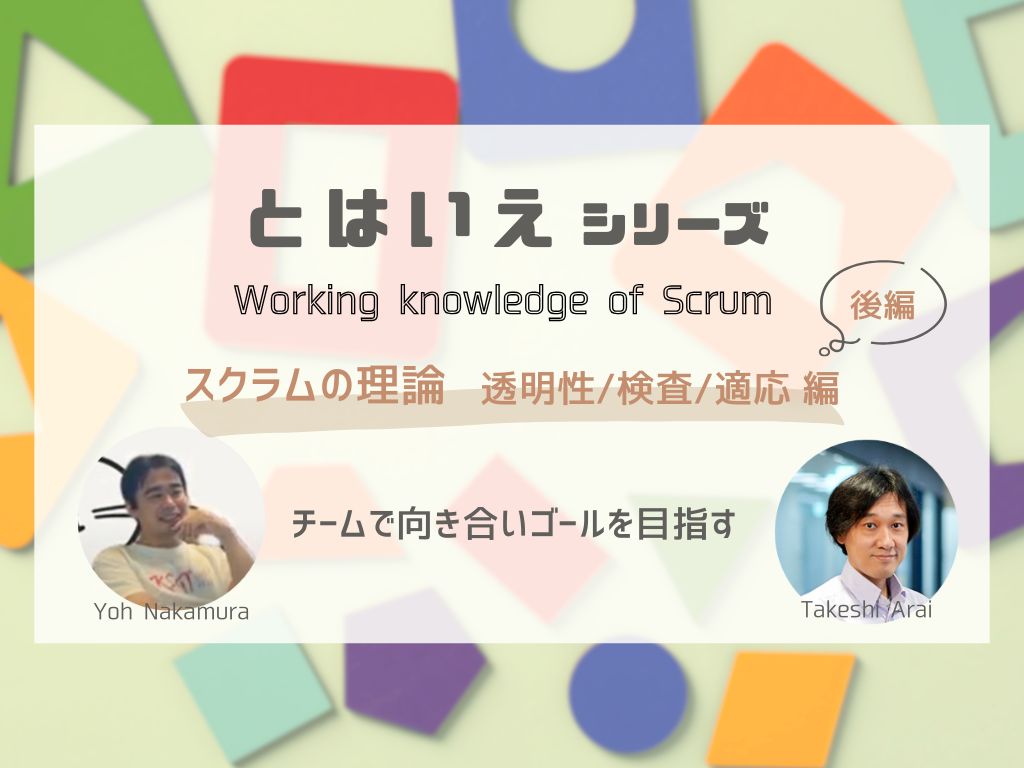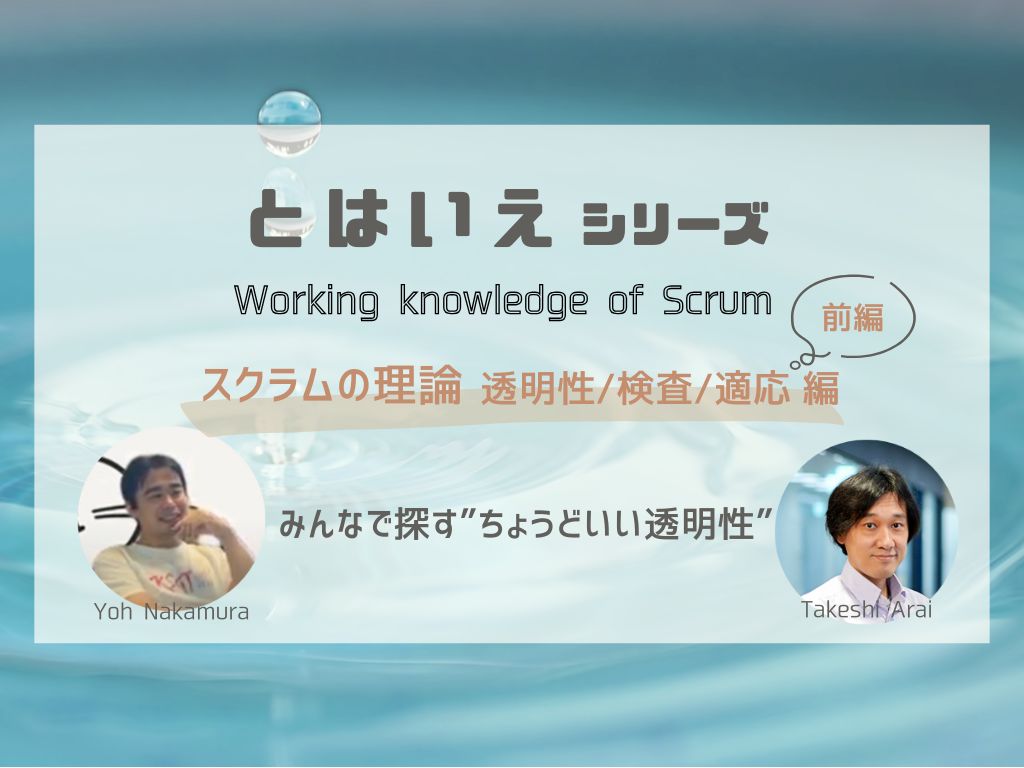“とはいえ”シリーズは、スクラムに取り組む現場で起こる様々な「とはいえ」をピックアップし、それぞれどのようにアプローチしていけばいいのか、レッドジャーニーの経験豊富なアジャイルコーチがざっくばらんに語るシリーズです。
「スクラムガイドにはこう書いてあるし、ブログではこういう事例を見かけるんだけど、とはいえ…」と困ってしまったり、チームで対話しても道筋が見えてこない時、ここでのお話が何か一つでもヒントになれば幸いです。
第13回のテーマは「スクラムの理論 透明性・検査・適応 編」です。後編では、「検査」と「適応」について深掘りしてお話します。
前編はこちら

新井 剛
Takeshi Arai
株式会社レッドジャーニー
取締役COO/アジャイルコーチ
CSP(認定スクラムプロフェッショナル)、CSM(認定スクラムマスター)、CSPO(認定プロダクトオーナー)

中村 洋
Yoh Nakamura
株式会社レッドジャーニー
執行役員/アジャイルコーチ
CSP-SM(認定プロフェッショナルスクラムマスター)、CSPO(認定プロダクトオーナー)
スクラムは、複雑なプロダクトを開発・提供・保守するためのフレームワークです。1990年代初頭、Ken Schwaber と Jeff Sutherland によって開発されました。
スクラムに取り組む際の拠り所となるのが、スクラムの定義やルールを示した「スクラムガイド」です。2010年に最初のバージョンが発表され、その後アップデートが加えられながら進化し続けています。
全18ページ(2020年版)という小さなガイドですが、目的や理論から実践まで分かりやすくまとめられており、スクラムの本質が理解できるようになっています。
「スクラムの理論」について、スクラムガイドには次のように解説されています。
スクラムは「経験主義」と「リーン思考」に基づいている。経験主義では、知識は経験から⽣まれ、意思決定は観察に基づく。リーン思考では、ムダを省き、本質に集中する。
スクラムでは、予測可能性を最適化してリスクを制御するために、イテレーティブ(反復的)でインクリメンタル(漸進的)なアプローチを採⽤している。スクラムを構成するのは、作業に必要なすべてのスキルや専⾨知識をグループ全体として備える⼈たちである。また、必要に応じてそうしたスキルを共有または習得できる⼈たちである。
スクラムでは、検査と適応のための4つの正式なイベントを組み合わせている。それらを包含するイベントは「スプリント」と呼ばれる。これらのイベントが機能するのは、経験主義のスクラムの三本柱「透明性」「検査」「適応」を実現しているからである。
透明性
創発的なプロセスや作業は、作業を実⾏する⼈とその作業を受け取る⼈に⾒える必要がある。スクラムにおける重要な意思決定は、3つの正式な作成物を認知する状態に基づいている。透明性の低い作成物は、価値を低下させ、リスクを⾼める意思決定につながる可能性がある。
透明性によって検査が可能になる。透明性のない検査は、誤解を招き、ムダなものである。
検査
スクラムの作成物と合意されたゴールに向けた進捗状況は、頻繁かつ熱⼼に検査されなければならない。これは、潜在的に望ましくない変化や問題を検知するためである。スクラムでは、検査を⽀援するために、5つのイベントでリズムを提供している。
検査によって適応が可能になる。適応のない検査は意味がないとされる。スクラムのイベントは、変化を引き起こすように設計されている。
適応
プロセスのいずれかの側⾯が許容範囲を逸脱していたり、成果となるプロダクトが受け⼊れられなかったりしたときは、適⽤しているプロセスや製造している構成要素を調整する必要がある。それ以上の逸脱を最⼩限に抑えるため、できるだけ早く調整しなければならない。
関係者に権限が与えられていないときや、⾃⼰管理されていないときは、適応が難しくなる。スクラムチームは検査によって新しいことを学んだ瞬間に適応することが期待されている。
出典:スクラムガイド
…とはいえ、実際の現場ではガイド通りには進みませんし、そもそも書かれていないような事態も多々起こります。そうした「とはいえ」に、どのようにアプローチしていけば良いでしょうか。
検査について考える
「検査」の時間はつらい?
中村:
次に「検査」にまつわる”とはいえ”について考えてみたいと思います。
まず、検査というよりも責められている気がしてしまうとか、レトロスペクティブでの発言がしにくいなど、レビューの時間がつらいというお悩みがあるようです。
どうしてこうなっているのかが気になりますね。文化的にこうなのかもしれないし、以前のスクラムでのつらい過去があるかもしれないし。
新井:
この事象を対処するだけでは上手くいかないと思うし、短期的に一気に解消できることではなさそうですね。根本的な原因を探って、そして少しづつ文化を変える、状況を変える手を打っていかないといけないかな。
こうなってしまっている状況がそもそも問題かなと思うので、チームビルディングをするだとか、インセプションデッキを使ってチームの狙いがどこなのか探したり、ご近所さんを探せ※や、俺たちの”Aチーム”※などのワークに取り組んで、立ち返ってみるのもいいかもしれませんね。
※ご近所さんを探せ:インセプションデッキのワークの1つ。
チームの周辺にいるプロダクトづくりの関係者や顧客と、彼らの関心ごとを明らかにするプラクティス。
※俺たちの”Aチーム”:インセプションデッキのワークの1つ。
チームに必要なスキルやお金、時間について考えるプラクティス。
参加者のコメント:
誰かが状況を攻めるような発言をしてしまっているのでは?
新井:
そうかもしれません。詰問されているように感じているのかもしれませんよね。
中村:
言ってる人は「今週終わるはずだったのにどうしたのかな?」と思っているだけで、そこに誰かを意図的に攻める意味はないかもしれないけれど、聞き手によっては”終わるはずのものが終わらなかった”ということを責められているように感じるかもしれない。言葉遣いがとても難しいですね。
新井:
そうなんですよね。自分に「失敗したな。できなかった。」という後ろめたさが存在するときに今のような発言が出ると、責められているように感じることってありますよね。
中村:
だから、防衛反応として言い訳などが出ることも人間ですから仕方がないと思いますし、かといってそこで「終わってませんけど、なにか?」と開き直るのも違いますよね。チームとして終わらなかったことは事実として、次どうしていくかを考えたいですよね。
新井:
できなかったことは嬉しいことではないけれど、そんなに悪いことではなくて、それをそのまま放置して見なかったことにする方が問題です。そしてこれが発生しているのは、個人ではなくチームや仕組みの問題だと思います。そっと触れないでおこうという空気が流れがちですが、チームとしてきちんと向き合っていきましょうということなんですよね。
中村:
最近私が読んだ本に、こうなったことを責めるのではなく、みんながこの状況になることに加担したと考えてみようと書いてありました。
例えば「1週間前に終わるはずだったのに、終わらなかったのはなぜ?」と聞いている人も、「事前に大丈夫?」と聞くことをしなかった結果こうなることに加担したという考え方なんです。
つまり、”何かをした”もしくは”しなかった”、ゆえに、この状況になることに少しづつ加担したのだから、チームでこの状況に向き合いましょうということです。
新井:
なるほど。加担。いい言葉ですね。プラスの加担もあれば、気が付かなかった加担も、やらなかった加担もありますもんね。
参加者のコメント:
レビュー対象も「〇〇さんがつくったもの」じゃなくて「チームが作ったもの」という見方になれるといいですよね。
中村:
おっしゃる通りです。スプリントレビューでステークホルダーにデモを触ってもらうときにも、作った人以外の人が操作したり、説明したりできるようになっているといいなと思います。
例えば新井さんがつくったものでも、ステークホルダーからの質問には私もお応えすることができる、といったようにね。
新井:
個人という点ではなく、チームという面で向き合っている感じがいいですよね。
Message from coaches
- レビューで責められているように感じてしまうなら、まずは根本的な原因を探ってみよう。文化や状況を変えるために改めてチームビルディングに取り組んだり、インセプションデッキのワークで立ち返ってみるのもおすすめ。
- 問題が発生した時は、個人の問題ではなく、チームや仕組みの問題ととらえ、みんなで向き合っていこう。
”頻繁かつ熱心に検査する”ためのポイントとは?
新井:
では、”頻繁かつ熱心に検査する”ためのポイントは、どんなことだと思いますか?
中村:
テクノロジー面でいうと、やはり自動化とか、エンジニアリングを上手に使うことだと思います。毎回ログを開かなくても、ある程度インテグレーションするとデータが溜まっているといった仕組みを作ったり。あとは、検査する範囲を絞るとか、頻度を見直すといったこともポイントだと思います。
新井:
そうですね。エンジニアリング要素の部分でも人間的な側面でも、関心ごとの濃淡はあると思うので、それに合わせて検査・適応していくということができるといいですね。
中村:
私も昔は、取れるものは全部取ってみることで、自分たちが気づいていない変化や傾向について見えてくると話していました。今でもそれは一つのアプローチなのですが、やりすぎてしまうと検査疲れが起きてしまうこともあります。
ですから自分たちが関心があるもの、大事なもの、または自分が見逃しやすいと分かっているもの、ついつい忘れてしまうものに絞って検査していくのはどうかな?
参加者のコメント:
確かひとつ前の版のスクラムガイドには「検査しすぎて邪魔になったらダメよ」的なことが書いていたと思いますが、自動化の技術が発展したからその注意文言が外されたのかなーと思ってます。
中村:
最近ではいろいろなサービスで自分たちのメトリクス(様々な活動のデータを収集し、計算や分析を加えて、分かりやすくデータ化したもの)を取れるようになっているので、コスト自体は低くなっていると思います。
ただ人間の認知力が追いつかないといったこともあるので、一定以上になると、よく分からないということになることもあるかなと思います。
Message from coaches
- ”頻繁かつ熱心に検査する”ためには、エンジニアリングを使った仕組み作りや、各種サービスの活用がおすすめ。検査する範囲や頻度も見直して、検査疲れを回避しよう。
- 関心ごとの濃淡を見極めて、それに合わせた検査と適応に取り組もう。