7月21日に刊行された市谷聡啓による新著「組織を芯からアジャイルにする」。前作「デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー」に続きレビュワーをつとめてくださった、経済産業省 デジタル・トランスフォーメーション室 室長の吉田泰己様をお迎えし、「組織を芯からアジャイルにする」をテーマに市谷との対談を行いました。
行政組織が抱える喫緊の課題やルールとの付き合い方などについて、機知に富んだ指摘とアイディアが展開された前編に続き、後編では、課題を乗り越え日本の組織を「芯からアジャイルにする」ために欠かせないポイントを探るとともに、お互いの実践知に基づいて「コミュニティ」という場のもつ可能性について語り合いました。一人でも、ごく少人数からでも、始めること、行動してみることでつながりが生まれ広がっていくというメッセージは、組織を変えようと藻掻くすべての方の力になってくれるのではないでしょうか。
※役職、肩書は対談当時のものです。
前編はこちらです
「標準」や「常識」との付き合い方
市谷:もう一つ、厄介だと思うのは「標準」という考え方です。民間の組織では「標準」を作って従っていくのはよくある話ですが、その「標準」がいろんなことを変えるときの足枷になるのではないかと、本を書きながら考えていました。
「標準」のもとに最適化され、そこに合わせながら慣れ親しむ状況を、組織のなかにいる人達自身が作り、脈々と受け継いでいっている。細かいところまでは明文化されていないものの、認識として醸成されて組織における「常識」になっているようなことがありますよね。明文化されていない、人の意識下にあるものを相手にしなくてはならないというのは非常に厄介だと感じます。行政機関でもそういうところはあるのではないでしょうか?
吉田様:行政機関では新しいルールができるとそれに従う傾向があります。一方で、現場のローカルルール的なものは新しいルールで塗りかえようとしてもなかなか変わりません。インセンティブを作るとか、何か行動変容のためのメカニズムを取り入れないと変わらないように思います。
「標準」や「常識」のようなものって、便利な面もあると思うんです。何か行動しようと思ったときに、「これに従っていればいい」というものがあれば効率的にショートカットできますから、「あったらいいもの」でもあると思います。問題なのは「なぜそうなっているのか」を考えずに依存することです。外部環境が変化し、すでに非効率になっている常識に、変わらず依存し続けていることが問題だと気づき、「その標準はなぜあるのか?」という「Why」にちゃんと立ち返って、理解した上で使っているのかどうかが重要です。そこを意識できていないことが行政機関では多々あるような気がします。大企業でも同様なのかもしれませんね。
市谷:まさしくそうですね。その「標準」の「Why」は何なのか、それを変えていくための仕組みも問われると思います。脳裏によぎったのは「ガバナンス」という言葉です。ガバナンスは組織を整えるために必要ですし、「適宜変更を加えられるようにするためのガバナンスも効くのかどうか」というところも問われますよね。難しいところです。
自問自答することが変化のきっかけになる
市谷:課題を乗り越えるため、あるいは、この先に向けて組織に何が必要だと考えられていますか?
吉田様:先程お話した「Why」のようなところに気づける人を増やすことだと思います。自分が向き合っているビジネスや事業に対して、圧倒的当事者意識のようなものを持てていれば、疑問は常に湧いてくると思うんですね。「なぜこんな非効率な作業をしているのか?」「なぜ利用者はこのサービスを使ってくれないのだろうか?」ということを考えていれば、それに合わせて行動しようというモチベーションが湧くはずです。そういうモチベーションを持てる人をどうやって組織に増やしていくのか。その次のステップとして、まさに今回の本で書いていただいているような、アジャイルな手法による組織変革や行動変容が必要になるのかな。そこはセットじゃないかと思います。
市谷:「自分は一体何者なのか?」という問いにどう答えるのか、自分を再定義することによって、「このままでいいのか」「このままじゃダメなんじゃないか」ということに気づけたり見出せたりすることがあると思います。だからこそ、この問いが大事で、そもそもの自分の役割や果たさなくてはならないこととは何だったのか、自問自答することが変化のきっかけになるのかなと思います。
大きな組織で、研修などを通してアジャイルの動き方や振る舞い方をお伝えすると、それを得た人たちはそれぞれ自分の仕事のなかでアジャイルを適用していきます。一方で、そういった「すべ」を「伝えていく側の役割」も必要なのですが、そこを増やすのは非常に大変です。通常、組織にいる人達には自分たちの仕事があり、具体的なミッションの達成のために仕事をしています。アジャイルを組織に広げることが直接的なミッションではないわけですから、そんななかで「一緒にアジャイルを広げていきましょう」と言っても、巻きこむのは思いのほか難しいとあらためて感じています。
ミドルマネジメントの理解度がキーポイント
市谷:吉田さんは、アジャイルを広げることがミッションというわけではなく、組織をよりいい方向へもっていくために必要だから実践したり伝えたりされていると思うのですが、どんなことを感じていらっしゃいますか?
吉田様:手法としては、今回の本に書かれているように、トップダウン的なアプローチとボトムアップ的なアプローチの両方が必要なのだろうと思います。トップが意義を理解し、そこに注力するという意思決定をした上で取り組むことと、草の根的なコミュニティのなかで進めていくこと、両面からアプローチしていくときに、これも本に書かれていることですが、ミドルマネジメントがそこをちゃんと理解しているかという点がキーになるのではないでしょうか。この層がどれだけアジャイルに動けるか。その度合いが組織のパフォーマンスに直接反映されると感じます。組織の上も下も意味を理解し本気で取り組もうとしているのに、ミドルが理解していないことで止まってしまうケースは少なくありません。行政組織を見ていても、その点がネックだと感じる場面がかなりあります。
市谷:今の日本の組織において意図的に変わっていこうとするならば、ミドルマネージャーたちが、自分の部署としてのミッションを持ちつつ、組織自体を変えていくための活動も日々の業務に織り込めるように、ミッションの置き方を工夫しないとなかなか変われないのではないかと感じます。
吉田様:本で書かれている「重ね合わせ」ということだと思うのですが、トップの意図を”実行する場”にどう重ねていくか。そこを担っているのがミドルの人たちで、トップの意図を正しく現場に伝えることができないといけないし、同時に、現場で実行して学んだ共有知をどうやって組織全体に広げてトップマネジメントまで上げていくのかということも考えなくてはなりません。迂回せず必ず真ん中を経由するのですから、やはりミドルがキーポイントなのではないでしょうか。
組織をアジャイルにすることで起こる変化
市谷:「アジャイル」の何が組織にいきるのか、組織を「アジャイルにする」と組織はどんな風に変わるのかについては、どうお考えですか?
吉田様:組織として環境の変化にどう対応するのか、それをいかに素早くできるかということではないでしょうか。年度計画や中期計画、四半期計画でも対応しきれないほど状況が激しく変化するなかで、すぐに対応できる組織にしていくには、実践から学び、学んだことを追加しながらいかしていくような姿勢がないと難しいと思います。
ひるがえって言うと、それぞれがある程度自律的に行動できる、セルフスターターとして行動できることが求められているということだと思います。情報伝達を待っていては、現場での対応が追いつきません。トップマネジメントが一つ一つ細かく指示しなくても、個人や事業部それぞれが環境変化を理解し自律的に対応できる必要があります。そういう状況を自律的に生み出せるのが「アジャイル」な組織なのでしょうし、「アジャイルにする」ことで環境変化のリスクに組織が対応していけるというメリットがあるのだと思います。
市谷:ミドルや現場が隅々までトップの考えている通りに合わせるのは現実的ではありませんし、恐らくいい結果も生まれません。合わせるところと委ねるところのバランスが大事です。本のなかでも、「意図」と「方針」と「実行」という三つの概念でトップとミドルと現場をつなげていくことについて書いています。
トップ、ミドル、現場の各レイヤーごとに扱える情報の解像度が違うんですよね。トップが描いている解像度と、現場で実行するために必要な解像度とでは全然違いますから、直接コミュニケーションをとろうとしても、なかなかかみ合わないはずです。その辺のバランスをどうとるのか、ぜひ本を参考にしていただければと思います。
「コミュニティ」という場のもつ可能性
市谷:「組織をアジャイルにする」ことの困難さについては、どうお考えでしょうか?
吉田様:自分で実行することや、実行して一回転まわすところまでの初動が一番大変で、そこをどう後押しできるかが本当に難しいところではないでしょうか。特に役所は失敗をおそれるカルチャーが非常に強いので、「考えてはいるけど実行していない」ことがよくあります。最初の一押しができる人をどれだけ作れるか。意志を持った人に共感して一緒に動く人が集まるという意味では、コミュニティがあることも重要なのかなと思います。
市谷:20年前、ソフトウェア開発でアジャイルに取り組もうとしたときのことを思い出します。当時は日本でアジャイルをやっている人なんて皆無で、自分の組織でやろうとしても最初の一押しが全然まわる気がしないし、実際やってみるとまあまあ失敗するわけです。組織のなかでは話しづらい分、外で有志が集まって話をしたのがアジャイルコミュニティのはじまりだったと思います。失敗談を語り合うことで、随分助けられました。
組織や開発以外の業務でも同様に、非公式な集まりでの情報共有が必要なのかもしれません。とはいえ、20年前のソフトウェア開発と同じように苦労する必要はありません。「アジャイル」という言葉は当時よりも流布していますから、組織のなかでも語り合う場を作れるかもしれません。行政のなかでもアジャイルを広げるための勉強会があったような気がしますが、例えば省庁を越えたコミュニティでアジャイルを広げていくというのは難しそうでしょうか?
吉田様:意志を持った人同士がつながることは可能だと思います。実際に経産省時代は「Govtech Conference」というイベントを自分たちで開催し、関心のある行政組織や自治体の人など、いろんなバックグラウンドの人が集まって議論したり、どうやって新しい考え方を取り入れていくのかをお互いに学び合う場を設けたりしていました。最近も、関心を持っている人たちでつながって、お互いにベストプラクティスをシェアし合うということを始めています。この輪が広がっていけば、もっと加速度的に変えていけるのではないでしょうか。
カイゼン・ジャーニー・メソッドのすすめ
市谷:組織内コミュニティのイメージで部門を越えて集まる輪を作り、そこで最初の一押しができると、前進する力になるのではないでしょうか。なかなか人が集まらないこともあるでしょうが、それでいいと思います。書籍「カイゼン・ジャーニー」で描いたことは現実の話です。自分ともう一人くらいのごく少人数から最初の一押しを推していき、そこから広げていけたらいいと思います。少人数ならではの”やりやすさ”もあります。そんな「カイゼン・ジャーニー・メソッド」とも言うべきアプローチがいいと思っています。
ただ、それだけでは自分たちのやっていることが合っているのか分からないままで心細かったりしますので、そういう時は組織の外の力も借りましょう。コミュニティで外の人たちと学び合いながら前に進めたらいいですね。
今日は共感しうなずきながらお話をうかがいました。非常に学びが多かったです。最後に一言メッセージをいただけたらと思います。
吉田様:私自身もまだ学びながらやっている立場でもあります。デジタル庁という組織自体が、まさに行政組織のなかでも本にあるような「アジャイルな組織」に変えられる可能性が非常に高い場所だと思っています。それに向けて本を読みながらいろいろトライしていきたいと思っています。今日はありがとうございました。
市谷:ソフトウェア開発でも、組織を越えて学び合い乗り越えられたことが多々ありました。これからの日本の組織について考えたとき、組織を越え、業界をも越えて、学び合えることがあると思います。意図的にそうしていく必要がありますし、そういうコミュニティをつくっていけたらと思います。皆さんもぜひ引き続きご参加ください。今日はありがとうございました。
Q&A
自分の部署ではない別の部署に問題意識がある場合、そこにアプローチするには?
外からの支援が「変わるモメンタム」になりえると思います。自分の部署がすでに問題意識を持ち取り組んでいるのであれば、そのナレッジをシェアすることで、新しいカルチャーを作っていく一つのきっかけになるかもしれません。(吉田様)
自分の部署ではないことで直接働きかけづらいのだとしたら、社内勉強会などの非公式な場や機会を作り、間接的に支援するというアプローチもいいと思います。(市谷)
行政の現場でもスクラムマスターやアジャイルコーチといった役割の方は活躍しているのでしょうか?
今はまだほとんどいませんが、様々な課題感から内製開発を取り入れていこうという議論が出てきていますので、そうなれば必要になるだろうと思っています。(吉田様)
前編はこちらです
組織を変えようと藻掻く、すべての人たちへ
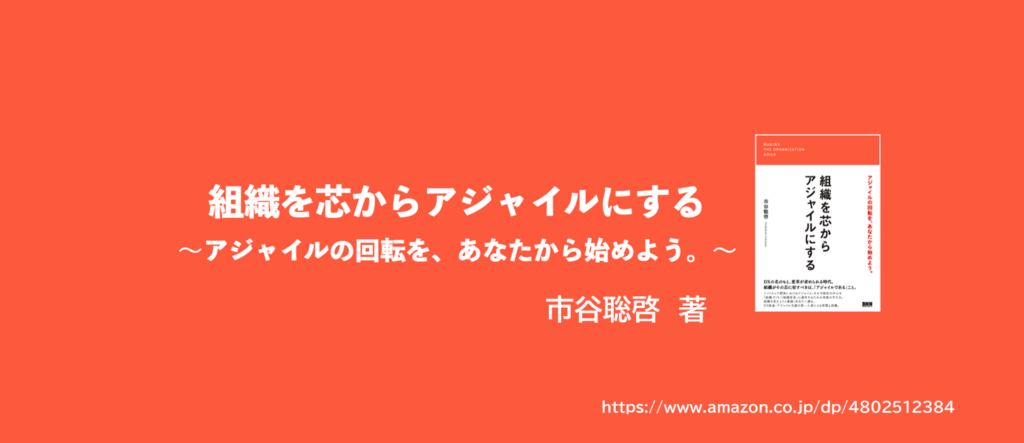
DXの名のもと、変革が求められる時代。
組織がその芯に宿すべきは、「アジャイルである」こと。
本書は、ソフトウェア開発におけるアジャイルのエッセンスを、「組織づくり・組織変革」に適用するための指南書です。
ソフトウェア開発の現場で試行錯誤を繰り返しながら培われてきたアジャイルの本質的価値、すなわち「探索」と「適応」のためのすべを、DX推進部署や情報システム部門の方のみならず、非エンジニア/非IT系の職種の方にもわかりやすく解説しています。
アジャイル推進・DX支援を日本のさまざまな企業で手掛けてきた著者による、〈組織アジャイル〉の実践知が詰まった一冊です。
詳しくは特設ページをご覧ください

