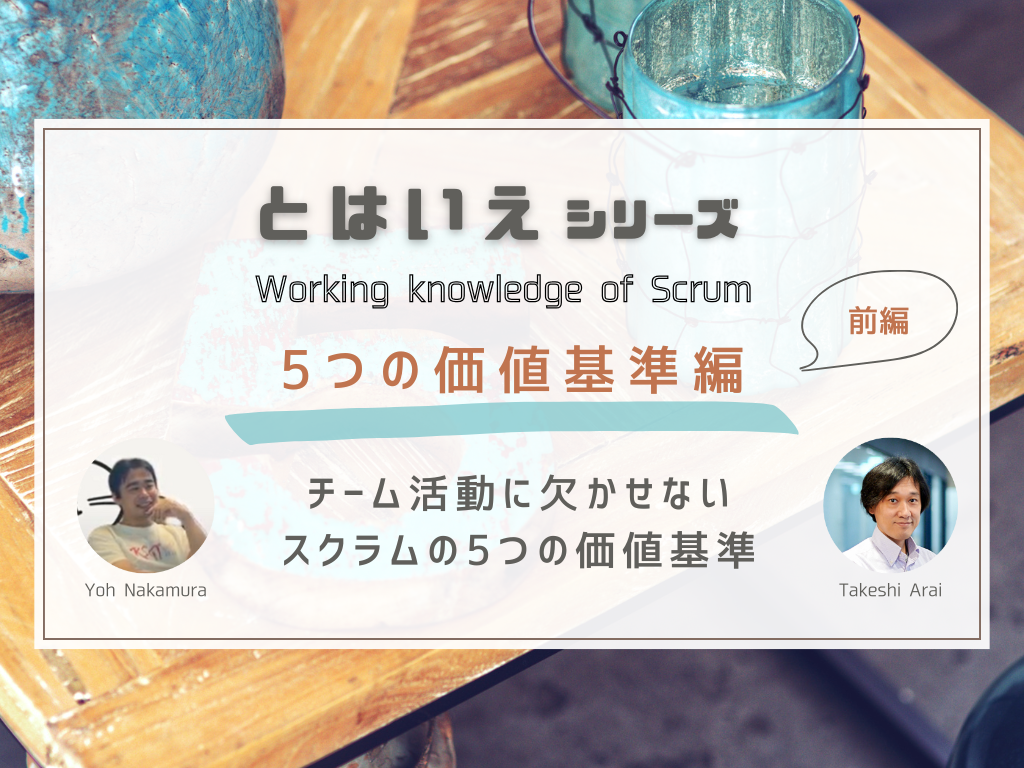期日を守ることも「確約」しなくてはならない?
新井:
上司やお客様との関係上、期日も約束する必要があることがほとんどですよね。
そんな時は、「幅」で合わせて「深さ」で調整するという方法があります。
例えば、ECサイトの会計の仕組みを今回のスプリントで完成させる場合、クレジットカード払いは恐らく必須でしょうけど、他の支払い方法などの「深さ」はある程度調整ができますよね。
中村:
アジャイルの文脈では、固定できる値は期日かスコープのどちらかだけなので、期日を約束するならスコープを可変にしてある程度柔軟性を持たせるというのが1つのアプローチですよね。
あるいは、期日までに出せそうなものを一旦約束して、その後、1週間〜2週間やってみて分かったことを基にアップデートしていくという進め方を提案することもできます。
新井:
勇気や尊敬、公開など他の価値基準にも関わってくるところですね。過去の回でも繰り返しお伝えしてきましたが、「誠実さ」が大事です。できないものをできると言ってしまうのは誠実ではないですよね。
中村:
マネージャーが期日を急かしたり無理な約束をさせたりすると、メンバーは間に合いそうにないことが分かりますから、本当に必要な作業を飛ばしちゃったり、余裕がなくなって品質が低下したりします。
期日を早く設定したからといって早くできるわけではありませんし、むしろ悪影響が出ることが多いので、マネージャーはシンプルに「ベストを尽くそう」と言うのがいいと思います。
参加者コメント:
「不確実なゴール」に向かって進んでいくことが前提である以上、期日を明確には約束できないと言うことは誠実な対応だと思います。もちろん、期日を約束できないことに対して甘えてはいけないと思いますが。
新井:
ベストを尽くすことが大前提ですよね。プロフェッショナルとして、受け取ったもの以上の価値を提供するという意識を持ち続けなければなりません。
中村:
アジャイルやスクラムは、プロフェッショナルとしての意識を持っている人々を対象にしている気がします。
今現在のスキルはそれほど問題じゃなくて、未熟なら学びながらやっていけばいい。
でも、分からないことは分からない、問題があることは問題があると、ちゃんとオープンにするという意識は絶対に持っていないといけないというのが前提だと思います。
Message from coaches
- アジャイルでは、固定できる値は期日かスコープのどちらか一方だけ。期日を約束する必要があるなら、スコープには柔軟性を持たせよう。
- 不確実性が高いゴールに対しては、その時点で確実と見込める範囲で期日を設定し、スクラムを回しながらアップデートしていく方法もある。上司やお客様に提案してみよう。
- 約束した期日に対してはベストを尽くそう。スキルが不足していたり、分からないことや問題があった場合には、それをオープンにする誠実さが大事。
作業に「集中」するために、どんなことができる?
中村:
シンプルに兼任・兼務をやめるというのはありますね。
新井:
他部署の人から声をかけられたり、チャットやメールでのやり取りが発生したり、突発的なことは必ず出てくるので、確保した時間をフルに使えるわけではないということを前提にしておくことも大事かな。
中村:
プロダクト開発やソフトウェア開発は特に高い集中力が要求されることが多いですから、疲れも蓄積していきます。
8時間みっちりプログラミングなんて基本的にはできないと思った方が良いし、他のことをする時間もちゃんと織り込んでおくのはいいですね。
新井:
「ブロックタイム」として外部からの干渉をシャットアウトする時間を確保するのもいいと思います。
中村:
「水曜日の午後は集中タイム」と決めて、ミーティングの予定を入れずにみんなで集中しているチームもあります。
新井:
共有カレンダー上でブロックしちゃうというのもいいですね。
中村:
時間の量は変えられないけど、質はある程度変えられます。
例えば、集中して作業できる時間帯をまとめて確保して、他のタスクはそれ以外の時間にまとめる。ミーティングを一箇所に集中させて、残りの時間を確保するというのもいいと思います。
新井:
30分の隙間時間でコーディングするのはなかなか難しいですからね。
中村:
1〜3時間くらいは欲しいところですよね。
集中するために周りの環境を整えるというのもいいと思います。作業が素早く進むように、会議室を貸し切ったりしてチームがリアルに集まって作業する場を作るとか。
新井:
それはすごくいいですね。個人で悩みを溜めこまずに気軽に聞ける場を作る。そこにプロダクトオーナーもいれば、仕様やゴールイメージを確認できたり意思決定してもらえるので、ちょっとした疑問点や悩みは即解決できますよね。
集中のための環境づくりは大事な視点だと思います。
中村:
ドキュメントなどに情報を事前に整理しておくことも、集中を維持するための重要な要素だと思います。
Message from coaches
- まずは、兼任・兼務を解消できないか見直してみよう。
- 確保した時間をフルに使えるわけではない。コミュニケーションや突発的なことにも対応できる余白をあらかじめ見越しておこう。
- 時間の量だけではなく質にも着目してみよう。ミーティングの時間帯をまとめるなど、集中力が必要な作業をする時間と、それ以外のことをする時間を分けるのも一つの方法。
- 外部からの干渉をシャットアウトする「ブロックタイム」を設けるのもおすすめ。共有カレンダー上でブロックするのもあり。
- 時にはチームがリアルに集まって一斉に作業する場を設けることで、疑問点や問題点を個人で抱えず即解決することができる。
- 集中のための環境づくりが大事。必要な情報はドキュメントなどに事前に整理しておこう。
作業に集中しすぎると周りが見えなくなってしまう
新井:
集中することで副作用的に不都合が生じることがあるかもしれませんが、それは別のところでカバーしていけばいいんじゃないかな。
中村:
みんなで集中してしまうと、必要な情報まで遮断されてしまうんじゃないかということですよね。
そういう時は、デイリースクラムでプロダクトオーナーやスクラムマスター、ステークホルダーからチーム外の情報を伝えてもらうようにするだけでも違うと思いますよ。
新井:
以前、あるチームが毎朝10時から15分間のデイリースクラムを始めたのですが、他のチームのみんなは10時に出社していたので、ちょうどその時間帯に内線電話がかかってくるんですよ。
最初のうちは内線が入るたびに「デイリースクラムをしているから」と電話を切っていたんですけど、ちょっと反感をかってしまったりもして。
でも、だんだん浸透してきて、他のチームにもデイリースクラムの習慣が波及していくと、10時から15分間は内線電話をかけないという社内ルールができあがっていきました。
「電話をしないでくれ」と言ったわけではないんですが、マジョリティ化したことで新しく暗黙のルールができていったのは面白かったですね。
中村:
内線電話みたいな外部からの情報はスクラムマスターが一旦受けとめるという形で集中を促すのもいいと思います。プロダクトオーナーを含めたメンバーは集中していいよという環境を作る。
新井:
ガード役、防波堤みたいな役割の人がいてくれると、集中しやすくなりますね。
世界的なインフラトラブルとか、よほど大きなことがあれば何をおいても対応しなくてはなりませんが、そこまでの出来事なら集中していても何かしら伝わってくるはずですから(笑)、あまり心配しなくて大丈夫じゃないでしょうか。
Message from coaches
- 集中することで生じる不都合は、別のところでリカバリーできないか考えてみよう。
- 集中している間の外部情報は、プロダクトオーナーやスクラムマスター、ステークホルダーからデイリースクラムで伝えてもらおう。
- スクラムマスターが一時的に情報を受けとめることで、メンバーが集中できる環境を作るのもおすすめ。