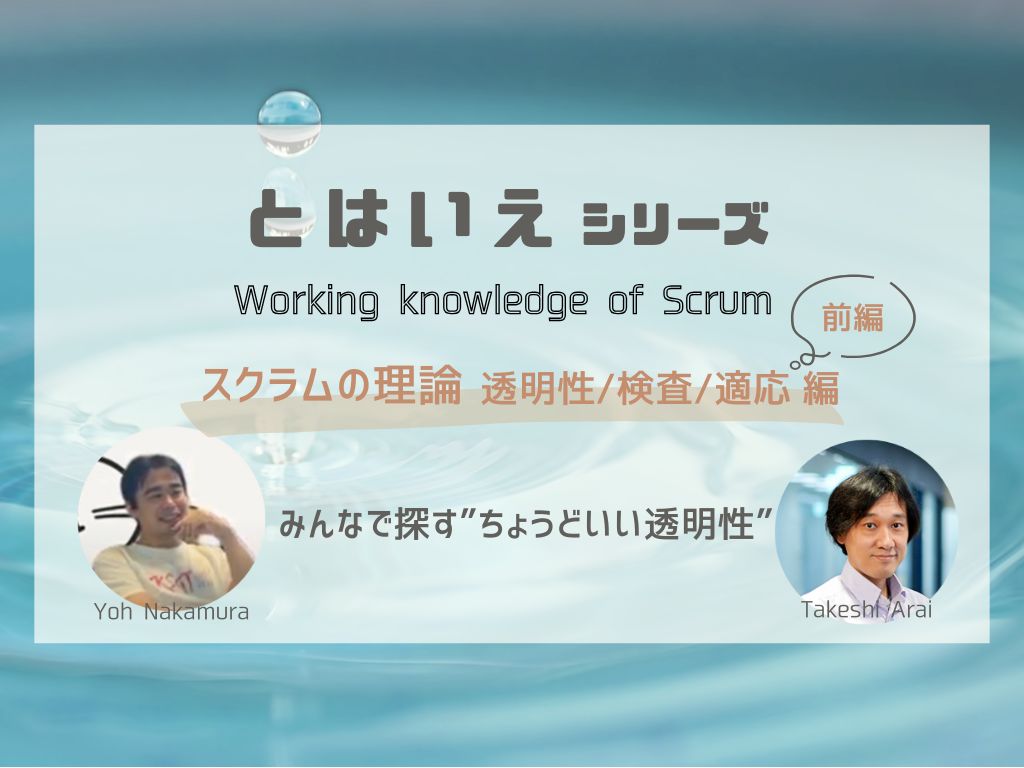“とはいえ”シリーズは、スクラムに取り組む現場で起こる様々な「とはいえ」をピックアップし、それぞれどのようにアプローチしていけばいいのか、レッドジャーニーの経験豊富なアジャイルコーチがざっくばらんに語るシリーズです。
「スクラムガイドにはこう書いてあるし、ブログではこういう事例を見かけるんだけど、とはいえ…」と困ってしまったり、チームで対話しても道筋が見えてこない時、ここでのお話が何か一つでもヒントになれば幸いです。
第13回のテーマは「スクラムの理論 透明性・検査・適応 編」です。前編では、スクラムにおける「経験主義」の考え方と「透明性」について、ご参加者様のコメントを交えながらお話します。

新井 剛
Takeshi Arai
株式会社レッドジャーニー
取締役COO/アジャイルコーチ
CSP(認定スクラムプロフェッショナル)、CSM(認定スクラムマスター)、CSPO(認定プロダクトオーナー)

中村 洋
Yoh Nakamura
株式会社レッドジャーニー
執行役員/アジャイルコーチ
CSP-SM(認定プロフェッショナルスクラムマスター)、CSPO(認定プロダクトオーナー)
スクラムは、複雑なプロダクトを開発・提供・保守するためのフレームワークです。1990年代初頭、Ken Schwaber と Jeff Sutherland によって開発されました。
スクラムに取り組む際の拠り所となるのが、スクラムの定義やルールを示した「スクラムガイド」です。2010年に最初のバージョンが発表され、その後アップデートが加えられながら進化し続けています。
全18ページ(2020年版)という小さなガイドですが、目的や理論から実践まで分かりやすくまとめられており、スクラムの本質が理解できるようになっています。
「スクラムの理論」について、スクラムガイドには次のように解説されています。
スクラムは「経験主義」と「リーン思考」に基づいている。経験主義では、知識は経験から⽣まれ、意思決定は観察に基づく。リーン思考では、ムダを省き、本質に集中する。
スクラムでは、予測可能性を最適化してリスクを制御するために、イテレーティブ(反復的)でインクリメンタル(漸進的)なアプローチを採⽤している。スクラムを構成するのは、作業に必要なすべてのスキルや専⾨知識をグループ全体として備える⼈たちである。また、必要に応じてそうしたスキルを共有または習得できる⼈たちである。
スクラムでは、検査と適応のための4つの正式なイベントを組み合わせている。それらを包含するイベントは「スプリント」と呼ばれる。これらのイベントが機能するのは、経験主義のスクラムの三本柱「透明性」「検査」「適応」を実現しているからである。
透明性
創発的なプロセスや作業は、作業を実⾏する⼈とその作業を受け取る⼈に⾒える必要がある。スクラムにおける重要な意思決定は、3つの正式な作成物を認知する状態に基づいている。透明性の低い作成物は、価値を低下させ、リスクを⾼める意思決定につながる可能性がある。
透明性によって検査が可能になる。透明性のない検査は、誤解を招き、ムダなものである。
検査
スクラムの作成物と合意されたゴールに向けた進捗状況は、頻繁かつ熱⼼に検査されなければならない。これは、潜在的に望ましくない変化や問題を検知するためである。スクラムでは、検査を⽀援するために、5つのイベントでリズムを提供している。
検査によって適応が可能になる。適応のない検査は意味がないとされる。スクラムのイベントは、変化を引き起こすように設計されている。
適応
プロセスのいずれかの側⾯が許容範囲を逸脱していたり、成果となるプロダクトが受け⼊れられなかったりしたときは、適⽤しているプロセスや製造している構成要素を調整する必要がある。それ以上の逸脱を最⼩限に抑えるため、できるだけ早く調整しなければならない。
関係者に権限が与えられていないときや、⾃⼰管理されていないときは、適応が難しくなる。スクラムチームは検査によって新しいことを学んだ瞬間に適応することが期待されている。
出典:スクラムガイド
…とはいえ、実際の現場ではガイド通りには進みませんし、そもそも書かれていないような事態も多々起こります。そうした「とはいえ」に、どのようにアプローチしていけば良いでしょうか。
経験主義について考える
新井:
今回のテーマは「スクラムの理論」なので、スクラムを始めたばかりの方や、もう一度学び直してみようという方に多く来ていただいているのかもしれません。嬉しいですね。
中村:
そうですね。今日は「スクラムの理論」の中でも、「経験主義」や「リーン思考」、そしてスクラムの三本柱である「透明性」「検査」「適応」の話をできればと思っています。どうぞよろしくお願いします。
「経験主義」とは、それぞれの経験を持ち寄ることですか?
中村:
スクラムガイドの「スクラムの理論」の冒頭に、「経験主義では、知識は経験から生まれ、意思決定は観察に基づく」と書いてあります。ここでいう知識や経験とは、メンバーの過去からくるものではなく、そのスクラムチームの営みの中で起きたこと、観察できたこと、学んだことだと考えます。
ですから「私は以前これを経験したことがある。」というのはスクラムの経験主義の真ん中からはそれているのではないか思います。あくまで今のチームとして経験して観察できたことが、スクラムの経験主義の中心かなと考えています。
新井:
そうですね。個人的な過去の経験というよりも、そのチームが組成された段階や、スプリント1が始まってから発生していること、目にしたもの、耳にしたこと、触ったもののすべて、ということですよね。
中村:
そうですね。私は経験主義を説明するときに「三現主義」というお話をします。「現場に行って、現物を見て、現実を見る。」という3つの”現”です。現場・現物・現実から生まれることこそが経験主義だと考えると、チームの外の人が「私の経験では…」と話すこともスクラムの経験主義そのものではないと思います。
新井:
なるほど。ただプランニングポーカーなどでは、自分の過去の経験から、現在の立ち位置でこのタスクの規模感は8かな?無限大かな?と考えるじゃないですか。そういった場合は否定するものでもないかなと感じるのですが、どうですか?
中村:
もちろんそうですね。ただ、そういった場合に注意が必要なのは、その経験を積んだ時のコンテキスト(状況や背景)は今とは違いますよ、ということです。
その人が別のチームで取り組んでいたプロダクトや、そのときの仲間や状況で感じたことは、現在とはだいぶ違うと思うんです。時間がたっていればなおさらですよね。ですから、その経験を今のチームで活用するかどうかについては、しっかり考えて気をつけてねとお話しています。
新井:
過去の経験に言いなりになってしまったり、「あの人が言っているからそのとおりにしよう。」というのはよくないですからね。いま起きていることをしっかり見て、「今回はそのリスクは高くないから大丈夫。」といった会話ができるといいですよね。
参加者のコメント:
スプリント開始当初はチームとしての経験の蓄積が浅いと思うので、それを個人の過去の経験で補完するのはアリだと思うのですが、スプリントを重ねたら、チームとしての経験が蓄積できるので、徐々にそちらに重心を移すことになる気がしました。
中村:
コメントありがとうございます。確かにそうですね。
おっしゃるようにスプリントスタート当初は、それぞれの経験を持ち寄るというアプローチもありだと思います。私も以前はそのように進めることもありました。
ただ、それぞれ違う状況で得た経験を、今の現場ですり合わせることはかなり難しい領域なので、最近は「過去の経験を持ち寄るよりも、まずは1スプリント、2スプリント回してみましょう。」とお話することが多いです。
メンバーのこれまでの経験やスキルについて知ってはいるけれど、それを今このチームでどれだけ活かせるかは分からない。だから、まずスプリント1では見積りも予測も立てないでベストを尽くしてみよう。そしてスプリント2は、そこから分かったこと(スプリント1の経験)を活かして回してみようというアプローチです。さすがにこの戦略には少々勇気が必要なのですが(笑)。
新井:
興味深いアプローチですね。良いものを集めたからといっておいしい料理ができるとは限らないですからね。
中村:
そうなんです。そのチームや目の前のプロダクトに相対している中で生まれる経験主義こそ大事にしたいなと思うようになりました。
Message from coaches
- スクラムの経験主義でいう知識や経験とは、そのスクラムチームの営みの中で起きたことや、観察できたこと、学んだことであり、個人の過去の経験やスキルを持ち寄ることではない。
- 過去の経験は、プランニングポーカーなどで自分の現在の立ち位置を考える際には否定するものではないが、そこから得られた情報を取り入れるかどうかは慎重に考えよう。
- スプリントのスタート当初はそれぞれの経験を持ち寄るというアプローチもあり。ただし、違う状況で得た経験を、今の現場ですり合わせることはかなり難しいので、まずは1スプリント、2スプリント回してみるのがおすすめ。
「経験主義」について知ってもらうには?
中村:
「社内の計画主義の圧力が強く、計画どおりに進んでいるかいつもチェックされている。」というお悩みもあるようです。
このような”とはいえ”を聞くといつも思うのですが、やはりスクラムチームだけがスクラムを理解すればいいということではなく、スクラムチームのステークホルダーや、マネージャー、経営者たちにもスクラムやアジャイルの取り組み方や大事にしている価値について知ってもらう必要がありますね。
新井:
そうですね。その認識が合っていないと計画主義に倒れすぎてしまいます。全く計画しないわけではないし、必要なゴールやスコープなども握らなくてはいけない。ステークホルダーの心配事にも考慮しながら進めていくことが、とても大事なことだなと思いますね。
ステークホルダーとしても、ビジネスという側面での関心事が存在しています。それをアジャイルだから、スクラムだからとないがしろにしていいわけではありません。
そのあたりはプロダクトオーナーが把握しながら、QCDS(Quality:品質・Cost:コスト・Delivery:納期・Scope:スコープ)のどこを守っていくか、どこの優先順位が高いのか、トレードオフ・スライダー※などで話し合い、決めながら、プロダクトの優先順位の高い順にリリースできたらいいかなと思います。
※トレードオフ・スライダー:インセプションデッキのワークのひとつ。
品質・予算・納期・スコープなどのプロジェクトの判断基準の優先順位を決める際のプラクティス。
参加者のコメント:
スクラムやアジャイルは計画しないという誤解がある気がします。
中長期という観点では計画して無いように見えるかもしれませんが、個人的には計画し続けていると思うのですが、どうでしょう?
中村:
これもいいご意見です。ありがとうございます。
アジャイルソフトウエア開発宣言の中に「計画に従うことよりも変化への対応を」と書いてありますが、ここには”計画しない”とは書いていないんです。
むしろアジャイルはゴール思考なので、ちゃんとゴールを見定めて計画を頻繁にアップデートし続けていきますから、最初にすべてを決めてしまう計画駆動といわれる方法よりも、はるかに細かく頻繁に計画し続けていると思います。
新井:
ステークホルダーの方たちに、そういった”計画しないという誤解”があるとしたら、解いていきたいですね。
参加者のコメント:
中長期的な計画も、「見通し」という形で立ててはいるんじゃないかなぁと思いました。ただ、検査を通して計画はどんどん更新されていくイメージです。
中村:
そうですね。この後ろの部分がとても大事で、計画は立てるし、こうなるといいよね、こうしたいよねという目標も立てます。それがないとみなさんが判断に困ってしまいますので。
ただ、おっしゃる通り、その計画が実現されるかどうかは、いろいろな場面で検査して、それをもとに変えていくようなことだと思います。
新井:
検査を通してアップデートしていく、解像度を高めていく、ということがスプリントごとに発生するのは、真摯に取り組んでいるということですよね。
やはり誠実であるべきだと思うんです。すごく遅れているのに「オンスケです。」というのは誠実ではないし、別のやり方が計画の解像度が高まるのにそれを放置しているとしたら、それも誠実ではない。見たのに見なかったことにしてそっと閉じるのではなく、勇気を持ってもう一度まな板の上に乗せてみましょう。
参加者のコメント:
そもそも経験主義は哲学などで出てくる認識論の立場のことだと理解していますが、スクラムガイドで書いている経験主義ってそれのことでは?
※認識論:哲学の一部門。認識の起源・構造・妥当性・限界などを論じる学問。
中村:
”哲学の認識論”については詳しくないのですが、言葉としてはそういうことかもしれません。
今起きていることに、ちゃんと目を向ける、観察できることを重視するという考え方だと思います。
新井:
そうですね。現場で起こったことに対して向き合っていきましょうということだと思います。
コメントありがとうございます!
Message from coaches
- ステークホルダーや組織のマネジメント、経営側の人たちにも、スクラムやアジャイルの取り組み方、大事にしている価値について知ってもらう必要がある。
- アジャイル開発では、ゴールを見定めて計画を頻繁にアップデートし続けているんだということをチーム外の人にも伝えて、”スクラムやアジャイルは計画しない”という誤解を解いていこう。
- スプリントごとの検査を通して計画を更新し、解像度を高め、真摯に取り組んでいるということを理解してもらおう。