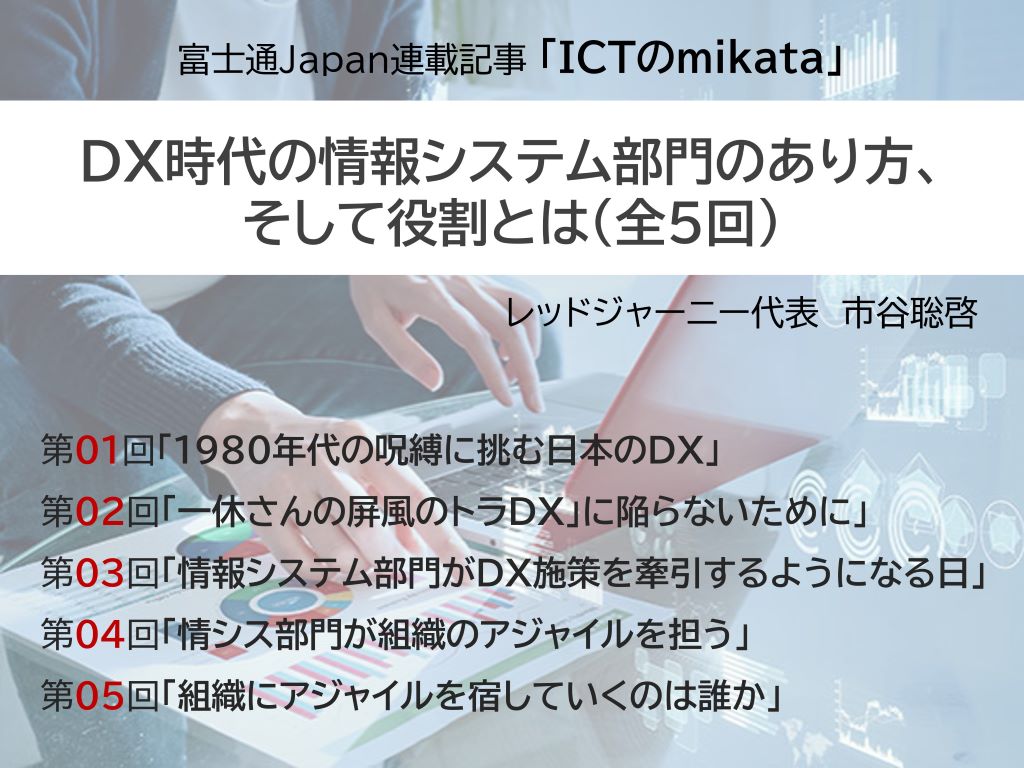代表の市谷による、富士通Japan「ICTのmikata」連載記事「DX時代の情報システム部門のあり方、そして役割とは」 全5回がただいま公開中です。ぜひご覧ください。
連載記事の一覧と概要
第01回 「1980年代の呪縛に挑む日本のDX」
DXに取り組む企業に求められることは、既存事業か新規事業かに依らず、探索のケイパビリティ(仮説検証&アジャイル)の獲得である。DXにおける一丁目一番地とも言うべき基本地点だが、実際に進めるにあたっては相当な困難に直面する。その背景には、日本企業がこれまで競争優位性を築くために磨き込んできた「選択肢を減らし、絞り込み、集中する深化の能力」があり、強みとしてきた能力が逆に足かせとなる現状をして、筆者は「1980年代の呪縛」と呼ぶ。
DXに取り組む組織は、この呪縛の存在を認識し、「組織の全般にわたって意思決定に影響を与えている」という状況を踏まえて変革にあたらなければならない。絶望的に感じられるかもしれないが、逆に言うと日本の組織内はやれることだらけ、探索能力の強化に関しては何を取り組んでも今より良くなる、と言えるわけで、1周回って、日本のDXには希望がある。この希望がかたちとなるよう、何を切り口にどう取り組んでいくのか本連載で解説していく。
第02回 「一休さんの屏風のトラDX」に陥らないために」
なぜ、日本企業においてDXが思うように進捗しないのか。様々な要因が挙げられるが、実際に組織を渡り歩いて気づいたのは「一休さんの屏風のトラ」ともいうべきDXの存在。絵に描いただけのDXで、その中身を実行に移すための算段、推進のプロセス、実行体制の現実感が乏しい状態のことである。さらに、DXの本質的な狙い(新たな顧客体験の創出)がきちんと理解できていればいるほどに、「いきなりDX」の罠にはまりがちだ。WHYはあっていても、HOWが圧倒的に不足している状況である。
より重要なのは、デジタル利用が仕事上の選択肢に当然のごとくあることで生まれる、「デジタルスタイル」とでも言うべき仕事に対する姿勢である。足元の仕事に対するスタイルが伴わなければ、そもそもDXとはどういう状態なのかという理解も深まらず、新規ビジネスやサービスの立ち上げなど、より難易度の高い仕事をスムーズに進めることは到底できない。
組織内でのITを担ってきた情報システム部門がこの状況を突破する一つの鍵になるが、旧態依然としたスタイルを守るだけでは情報システム部が組織変革で立ち位置を得ることは難しく、情報システム部自体も変革に向けた取り組みが必要となる。
第03回 「情報システム部門がDX施策を牽引するようになる日」
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発信している「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」を紐解くと、DX推進のための組織体制を構築するにあたって、4割の企業が専門組織を立ち上げていることが分かる。DX推進にあたっては専門組織の設置が一つの手がかりになると言えそうだ。
DX推進においては数多くのプロジェクトやテーマが並走することになり、その分チームやステークホルダーの数も多くなる。そうした混沌とした状況の中で、運営を支えるのがアジャイル、特に「スクラム」である。スクラムでプロジェクトを運営するにあたり、情シス部門はスクラムマスターを務めるのが適している。スクラムマスターとは、スクラムの運営が機能するよう各種働きかけを行う、サーヴァント・リーダーシップを体現する役割である。
実情としては情シス部門がスクラムの運営をリードするという状況が増えているとは言い難いはず。情シス部門がスクラムで実践的な役割を果たすためには、相応のケイパビリティを獲得するところから始める必要がある。
第04回 「情シス部門が組織のアジャイルを担う」
情報システム部門がDXの取り組みの中で役割を果たしていく鍵は、アジャイル開発、特にスクラムを習得することである。「DXのスクラムマスター」を務めることが、これからの情報システム部門の果たす役割と言える。
問題は、新たな役割を担えるほど情報システム部門に余裕が無いという現状である。既存の業務、システム保守に手一杯で、新たなスキルを身につけ、新たな取り組みにトライしていく時間が無い。こういった状況に対して、筆者は「はじめることをやめる、やめることをはじめる」という指針を打ち出すようにしている。
「やめることをはじめる」ことで、少しずつですが部門に余力を作ることができたら、そこからスクラムの習得へと乗り出していく。スクラムの習得も最短距離で取り組みたいものの、現実的にはこれまでとは違う仕事のスタイルを身につけるため、相応の時間を要する。「効率化」があらゆる判断基準に染み付いてしまっていると、スクラムのような「一定の期間ごとにやるべきことを見直し、判断を変えて進める」というスタイルは相容れないはずで、こうしたマインドチェンジを果たすために、組織の中に一つの建物を作るイメージを持ちながら段階的に取り組んでいく。
第05回 「組織にアジャイルを宿していくのは誰か」
DXにおける情報システム部門の新たな役割について提言を行ってきた本連載も今回で最終回。これまでの内容をふりかえり、新たな情シスに向けた最初の取り組みについて言及する。
日本の企業の多くが「1980年代からの呪縛」を背負っている。両利きの経営でいう「深化」のケイパビリティを磨き上げて、効率化を推進していくことが確立されたビジネスモデルの上では最善の戦略であった。いわゆる改善やPDCAという取り組みが強い日本を支えることになり、しかし、同時に足かせとなっているのが現状だ。
「深化」に最適化してきた組織では、新たなビジネスモデルを模索するために必要な「探索」のケイパビリティが育ちにくく、多くの企業で「DXで何から始めたら良いか分からない」という声が聞かれる。組織として取り組む選択肢を自らあげることができないという「探索」のケイパビリティの欠如の現れである。
この状況の突破口を握るのが、ITを本分として組織のイネーブラーを担う情報システム部門である。そこで求められる協働の型こそが「アジャイル」だ。アジャイルへの取り組みを進めていくために、情シス部門の一人ひとりのアジャイルな振る舞いそのものが必要である。「アジャイル」を学び、身につけるための取り組み自体を「アジャイル」に行う必要があると言える。アジャイルが情シス部門の牽引を通じて、組織の中に広がり、新たに組織を支えるケイパビリティとなっていく。イネーブラーとしての新たな役割が果たせるよう、まず情シス部門からアジャイルを始める必要がある。
DXの本質とは、組織を取り巻く環境がいかに変化したところで、それに適応できるすべを組織が身につけていくところにある。30年分にもなる組織の学習不全を返していくには1年や2年では済まないだろう。息の長い取り組みになるからこそ、一歩一歩自分たちが得ているものは何かを確かめながら組織変革の旅を続けていくことにしよう。
レッドジャーニーのDX支援
さまざまな企業や組織で試行錯誤されたDXへの取り組みについて、詳しい内容や課題、実施された取り組み、見えてきた展望などをインタビュー形式で記事にまとめています。ぜひご一読ください。